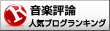行きつけのおでんバーに行って飲んでたんだけど誰も来ない。マスターと二人しか居ないのでこんな時は一般的ではない趣向の強いヤツをじっくり選んで聴くことが多いのです。このアルバムもマスターが奥からCDの箱を持ってきてゴソゴソとやってからフンフンと言いながらかけてくれたました。おでんバーでかけるのは洋ものが多いのです日本人ではマスターが好きな西荻窪にライヴハウス「アケタの店」のオーナーピアニストの明田川荘之などが良くかかっています。向井滋春を聞くのは久しぶりだったかもしれません。私も日本人アーチストはあまり知らないのですが向井滋春は大学の時にフュージョン時代の曲をコピーバンドでやっていたりしたんで、このトロンボーンの響きは、しっかり頭に焼き付いていて久しぶりに聴きながら懐かしい響きが心地よかったので借りてきてしまいました。
さて和ジャズのトロンボーンの第一人者向井滋春は1949年1月21日、名古屋生まれ。高校入学時に吹奏楽でトロンボーンを始め同志社大学でビッグバンド、コンボで腕を磨き、1970年にヤマハLMコンテスト入賞、'72年川崎僚バンド、大友義雄バンド、に参加しながら自己のバンドも結成。'79年にニューヨークに渡り、帰国後「モーニングフライト」を結成し「オリッサ」と改変、「渡辺香津美キリンバンド」「松岡直也ウイシング」にも参加されています。(ここら辺は私のツボです)その後ブラジリアン音楽のミュージシャンと共演したしながらエルビン・ジョーンズとのツアーを機に再びストレート・ジャズの世界に帰ってきて'86年に板橋文夫、古野光昭、古沢良治郎とこの「ホットセッション」を結成したわけです。
アルバムの印象は流行の音楽にも、その演奏を提供し続けているメンメンが明るく洒落っ気たっぷりに流行に媚びずに正々堂々と明るくおおらかにジャズしていることですね。洋ものには無い雰囲気が溢れていて日本人にはやはり共通の心があるんだなと感心してしまいます。また録音はかなに良くて、向井さんのトロンボーンの音色の変化が鮮やかに捉えられています。
Expression は、ベース古野の作品でストレートなジャズだけど粋なメロディーとテンポが嬉しい。決して和じゃないけど和を感じるんですよね。わかるかな~。Quiet Eyes は向井さんの作曲でトロンボーン・メインのバラードです。ロング・トーンが向井さん独特のビブラートとトリルが楽しめる構造ですね。Ojisan Korekara はピアノ板橋さんの作曲で、こうゆうユニゾンと決めの曲はジャズに限らず日本のこの時代のフュージョン系のバンドではよくあるパターンかと思われ、そういった意味で和を感じるかなあ。ああ楽しい。雨あがりの朝 はドラム古澤さんの楽曲で、幻想的な曲になっています。テーマのメロディーはどっかで聴いたことありますが思い出せない。童謡か?唱歌か?ですかね。I'm Getting Sentimental Over You は1934年に Tommy Dorsey and His Orchestra というビッグバンドで初演奏
され、 Tommy Dorsey's の死後にフランク・シナトラが残されたビッグバンドと共演して有名になった曲とのこと。ですが、これはドラムと向井さんの二人のバトル曲になっています。お好きなんですね。ヤンヤ、ヤンヤ。Limehouse Blues も昔のブルース・スタンダードで安定のリラックスナンバーです。ノリとしては Gadd Gang に近いようなアップテンポのファンク・ブルース仕立てで余裕の大人を感じます。Lady's Blues はソウルバラード系のジャズ・ブルース・スタンダード でこれも定番曲なのでしょうか。ひたすら余裕の色気のある演奏です。Half Moon でピアノ板橋さんの曲となりますが、ここでこのバラードは泣かせます。Landsat View で向井さんのオリジナルで、ジャズ色の中に向井フュージョン的なノリの現代的なアップテンポナンバーです。ジャズなんだけど違うんですよね。楽しかったアルバムもこれで終わり Drunk On The Moon です。スタンダードで締めるのか。最後にこれ聴いてもう一杯飲んでいってねって感じです。楽しい和ジャズの世界でした。おでんバーのマスターありがとうございます。
向井滋春 Trombone
板橋文夫 Piano
古野光昭 Bass
古澤良治郎 Drums
録音:1989年7月3~12日
オリジナル・リリース:1989/10/01 CY-3992
1. Expression
2. Quiet Eyes
3. Ojisan Korekara
4. 雨あがりの朝
5. I'm Getting Sentimental Over You
6. Limehouse Blues
7. Lady's Blues
8. Half Moon
9. Landsat View
10. Drunk On The Moon