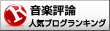ジャケ写違いで2枚持ってました
1作目「Just Between Us」も良いけど、1994年発表の2枚目の本作は、ブラコン的なニュアンスにポップさが加わってより聴きやすい仕上がりです。本作では8曲目 It Costs To Loveなどでボーカルもとっていますが、Georege Benson タイプの歌い方ではないのにホッとしくコンテンポラリーで単にソウル好きな感じがして好感。
発売は MoJazz と言うレーベルで、1992年に設立、1998年に閉鎖したモータウン系。同じくモータウンの他にもあった Workshop Jazz にも類似したレーベルのようです。MoJazz 所属アーチストは The Crusaders、Terra Sul 、Lionel Hampton、Foley など(The Crusadersしか知らんです)Norman Brown は、このあと 3作目 Better Days ahead をリリースしてからレーベルが閉鎖され、Warner Records と契約しています。
私のこのアルバム購入は、新譜で即購入ではなく発売から数年以内の購入。当時は今のようにギターレスのアルバムに興味が無くかったので、ギターアルバムばかりを買いあさっていました。その中でも、この After The Storm は、コンテンポラリーな中にファンクな要素の音楽感があり、ギターはジャズ素養がバリバリと入っている作風が、お気に入りのアルバムです。
それでは全曲聴きながらのレビューです。1曲目「Take Me There」オクターブ奏法全開のギターでコンテンポラリーな曲調、スラップベースに甘い声のバッキング・コーラス で、細かく動き回るギターソロはベンソンっぽいけど好きです。「After The Storm」キラキラとした音色のシンセがイントロから落ちてきて、爽やかなで優しいメロディーのテーマですが、カチッと細かく刻むフレーズとユルユルと流れるフレーズの組み合わせ。さすがテーマ曲です。後半の怒涛のギターソロも素晴らしい。強すぎないアタックなので聴きやすいですね。「 That's The Way Love Goes」 Janet Jackson の1993年の Virgin Record から発表の作品のカバーです(Motown ではないのを先ほど確認)。原曲には、James Brown の「Papa Don't Take No Mess」とThe Honeydrippers の「Impeach the President」をサンプリングされていて、宇多田ヒカルの「Addicted To You」のUnderwater Mixではこの曲のフレーズが使われているので、何かと耳に馴染みがあります。ちなみに宇多田ヒカルの楽曲自体は1999年11月10日のリリースでした。次いで「Any Love」は Luther Vandross のカバーになります。作曲には Marcus Miller も絡んでます。サビでコーラス部隊が参加してきてからインスト曲から歌物に変わってしまうアレンジが素晴らしい。「Lydian」歌ものっぽいノリからコンテンポラリー・ジャズに回帰します。曲名は、音楽で使われる Lydian Scale からとられているのでしょうか。この曲が、そのスケールが多用されているのかはよくわかりませんが。「 For The Love Of You」 Isley Borothers のカバーです。原曲を聴いたことが無かったので特に懐かしむような感想はありませんが、後半からのスキャットとフレージングは、やはり Norman Brown はベンソン好きなのだと再確認の曲でした。「Trashman」こうゆうマーカス的な作風は大好物です。単純にカッコ良いでいいじゃないか。「It Costs To Love」 歌物ですがカバーでは無いようです。スキだからやってます。歌いたいからやってます。自己満でわるいですか感が非常にあります。歌に全力振り切り完成度は高いです。売れなくても良いんです。「Let's Come Together」 イントロからギターのカッティングの音が変わり、シングルコイルの音がしますが、メロディーラインはいつものヤツです。「Acoustic Time」曲名のとおり、アコースティックギターの独奏です。YouTube動画などで Norman Brown の独奏を見ますが作り込みとアレンジが凄いです。「El Dulce Sol」曲名の字面でわかるようにラテン系で、跳ねるリズムにラテン独特のキメを混ぜながらテーマの切れ目切れ目の間が Norman Brown ってこの節回しがクセだなって聴きながら思いました。「Family」特に感想も無いですが、ライブとかで見ると楽しそうな楽曲です。「Man In The Mirror」言わずと知れた Michael Jackson のカバーを独奏でやってるのですが、これが素晴らしい。多分私がギター弾きであることもあって、かなりグサグサ刺さります🎶
日本のTV番組で演奏している映像がさらに良いので紹介しときます。
Norman Brown : guitars (1, 2, 5, 8, 9, 11, 12), guitar synth piano (1), backing vocals (1), arrangements (1–9, 11, 12), lead guitar (3, 4, 6, 7), rhythm guitar (3, 4, 6, 7), vocal arrangements (6, 8), wah-wah guitar (7), horn arrangements (7, 11), lead vocals (8), programming (9), keyboard bass (9), acoustic guitar (10)
Brian Simpson : keyboards (1, 7, 11), horn idea (7, 11)
Herman Jackson : keyboards (2, 4–6, 8, 12), acoustic piano (8), programming (9), keyboard bass (9)
Crayge Lindesay : vocal arrangements (1), keyboards (3), wah-wah guitar (3), bass (3), drum programming (3), arrangements (3)
Gail Johnson : keyboards (4, 6)
Larry Kimpel : bass (1, 7)
Freddie Washington : bass (2, 4, 6, 8, 12)
Tony Dumas : acoustic bass (5)
James Manning : bass (9)
George Lopez : bass (11)
Ricky Lawson : drums (1, 7)
Land Richards : drums (2, 4–6, 8, 11, 12), arrangements (4–6, 8)
Alonzo "Scotter" Powell : drums (9)
Munyungo Jackson : percussion (1, 4–6, 10, 11)
Gary Bias : alto saxophone (7, 11), tenor saxophone (7, 11)
Reggie Young : trombone (7, 11)
Ray Brown : flugelhorn (5, 12), trumpet (7, 11)
Steve McKeever : vocal arrangements (1)
Lynne Fiddmont-Lindsey : backing vocals (1, 4, 6, 8), vocal arrangements (4, 6, 8)
Bridgette Bryant-Fiddmont : backing vocals (4, 6)
Baby Lee : backing vocals (4, 6)
Arnold McCuller : backing vocals (4, 6)
DeNetria Champ : backing vocals (8), vocal arrangements (8)
executive-producer : Steve McKeever
producer : Norman Brown
released May 17, 1994
recoeded at Winsonic Process & Recording (Beverly Hills, California),Quintus Recording Studios (Hollywood, California)
1. Take Me There / Norman Brown
2. After The Storm / Norman Brown
3. That's The Way Love Goes / Jimmy Jam, Janet Jackson, Terry Lewis
4. Any Love / Marcus Miller, Luther Vandross
5. Lydian / Norman Brown
6. For The Love Of You / Ernie Isley, Marvin Isley, O'Kelly Isley, Ronald Isley, Rudolph Isley, Chris Jasper
7. Trashman / Norman Brown
8. It Costs To Love / Norman Brown, Les Colter
9. Let's Come Together / Norman Brown
10. Acoustic Time / Norman Brown
11. El Dulce Sol / Norman Brown
12. Family / Norman Brown
additional tracks
13. Man In The Mirror
▶ After The Storm
▶ Trashman