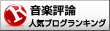2009年に結成10周年となったソウライヴのスタジオ録音盤では通算8枚目のアルバムで、音は少し重量級に変化しています。発売は Royal Family の1枚目です。発売レーベルは1999年デビュー盤から Royal Family で2枚、メジャーの Blue Note で2001年から2枚+ライブ1枚+コンピ1枚、2005年 Concord、2007年 Stax 1枚、そしてこの Up Here が2009年。スタジオ3枚、ライブ2枚を発売しています。
オルガン・ジャズ・インスト・ファンクが基本なので、ベースは無しのギター、ドラム、ギター、オルガンの基本構成に活動していましたが、前作 No Place Like Soul は、ボーカルのToussaint が加わって路線を変えたかと思いましたが、世の中では、賛否両論の否のほうが若干強めだったせいか、ボーカルナンバーを控えめにしたようです。ブラスは元々ゲストで参加している曲が多かったので全く気になりません。
本作ではファンクナンバーは、ブラスもタイトにアレンジで、アルバム自体は力強いサウンドが良い。最初はもの足りなかった印象ですが再度聴くと聴きごたえのある良いアルバム。
それでは全曲再度聴きながらレビューです。「Up Right」オーソドックスなジャズ・ファンクにブラスの加わって、現代風のダンサブルなビートも見えるナンバーで展開はソウライブ感があります。「The Swamp」ずっしりと重いビートに合わせピーピピとなる、オルガンの音が印象的です。音のうねりに合わせてギターがメロディを入れてきて、スパニッシュを感じるギターのリフが出てきたりします。「Too Much' 」ボーカルの Nigel Hall が張りのある歌声なので、JB的なノリですがBメロ部分で古き良き響き入っているのも何か懐かしい感じがします。コーラスもばっちり決まってます。「Backwards Jack」リフのベースラインの上下運動が気持ち良い曲です。テーマに明確なメロディ使わずにコードで曲が変化していくのが怪しい雰囲気のアシッドっぽい曲調になっているのも良いです。「 PJ's」は、Eric Krasno が弾きたい泣きのギターを思いっきり、ためてためて情を入れた曲になります。ゴリゴリのギターの印象の強い方ですが、泣きのギターも聞かせどころをわかっていらっしゃる。いや素晴らしい。「Tonight」懐かしきJBサウンドが、リフで Alan Evans が、身体を細かく震わせながら歌っているのが聴きながら見える気がします。ホーン部隊も絶好調ですが、このベースラインをオルガンのペダルだけで演奏しているのは驚異です。気持ち良し。「Hat Trick」これこれ、」このゆったりとしたグルーブと流れがソウライブらしいので安心します。こんな曲だとライブでは観客全体が揺れるんだろうなあと想像できます。「For Granted」ボーカル無しのJB+Grant Green パターン、流れるように出てくるギターやオルガンのお決まりフレーズが決まってます。サックスソロも良きです。ボーナストラックを除いて最後の曲は「 Prototype 」で、ドラムの Nigel Hall がボーカルをとります。歌いたかったんでしょう。スキなんでしょう。わかります。理解できます。そしてボーナストラックに突入「El Ron」サイケでダーク。観客の声が入っているのでライブ録音ですね。Steady Groovin' では、もっとストレートにゴリゴリのアレンジでした。「Reverb」もライブ録音です。スタジオ録音は Break Out に入ってます。イントロは何か違うダブの曲か何かを使っています。この録音はスタジオ盤のアレンジに近いものの、ビートのアクセントが変わっています。いやいや、このバンドやはり奥が深いですね🎶
drums : Alan Evans
guitar : Eric Krasno
keyboards : Neal Evans
sax : Ryan Zoidis, Sam Kininger
vocals : Nigel Hall (tracks: 3,9)
produced by Soulive
2009 Royal Family Recordings
1. Up Right
2. The Swamp
3. Too Much' (vocals : Nigel Hall)
4. Backwards Jack
5. PJ's
6. Tonight (vocals : Alan Evans)
7. Hat Trick
8. For Granted
9. Prototype (vocals : Nigel Hall)
【Bonus Tracks】
10. El Ron
11. Reverb
▶ PJ's