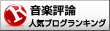2021年8月31日火曜日
本日のCD Thelonious Monk ♪ Underground
2021年8月30日月曜日
本日のCD Bill Evans ♪ Every body Digs
 |
2021年8月29日日曜日
本日のCD Eric Dolphy At The Five Spot Vol2
コロナワクチン2回目の接種
コロナ・ウイルスの感染は勢いを増して新規感染者は昨日8月28日もは22千人を超えています。大変なことになっているて、職場の出勤率は7割削減になりWEB会議での打ち合わせが当たり前になり、生活の様式は変化してきているのですが、実生活では死に至る可能性のある病がすぐそばの人に感染しているかもしれない危機感は希薄かもしれないです。できる感染対策はしているって感じですね。
結構今回の接種はきつかったんで記録を残しておきます。
午前11:30に接種を受けて、午後の勤務は「みなし勤務」として退社。現在の会社には出向しているので帰りがけに本籍のある会社によってみた。本籍のある会社は職域接種は行っていなかったので接種は完了している人がほぼいなかったのが印象的でした。1時間ほど滞在して会社を出たのは15:00ぐらいでしたが、全く体調に変調は無く「今夜も缶酎ハイ飲んで内販で買った食材をどうやってつまみに仕上げるか」などと思いながら帰宅。帰宅してからは最近購入したエレピの練習を30分ほどしてから少しだるいから横になって休んでからメシでもつくるかと寝入ってしましました。気が付くと 19:00 ぐらいで少し発熱して汗ばんでいます。だるいので夕食は作らずにアイス・コーヒーとお菓子で寝ることにします。
夜中の 1:00 に目が覚めると注射をした肩のあたりが「ずん」と痛くなってきていて若干の頭痛がします。当然、酎ハイを飲む元気はなく温水シャワーを浴びてから寝ます。寝苦しくて熟睡ができずに朝 4:00 からは眠れなくなり YouTube を見ながらゴロゴロとしながら朝を迎えます。今考えるとかなり体調が悪くなっていたのですが、気分が悪すぎて自分の体調がやばいと思うことすらできませんでした。
朝 8:30 ごろ接種から20時間経過でやっと熱が下がってきて就寝しました。午後14:00にはクリーニング屋と土曜日恒例のマッサージには行ったんですが体調がすぐれずに、固形物は摂らずに過ごしました。当然アルコールを飲む気分にもなれません。ピアノの練習とも思いましたが、肩が痛くて気分もすぐれず10分以下で敗退してベッドでゴロゴロでした。
本日日曜になり方に若干の痛みは残っているものの、固形物が食べたくなり朝食をとりました。ピアノの練習も1時間以上連続してできる集中力をとり戻しました。
私の接種したワクチンはモデルナです。ファイザーよりも副作用がきついとは聞いていたものの、これほどまできついとは思いませんでした。人間体調が悪くなると判断力も鈍りますので解熱剤も服用せずに体力を消耗してしまいましたので、これから受けられる方には簡単に食べられる軽食や鎮痛剤、飲み物を用意して少しでも楽に過ごすせるような準備をお勧めします。
2回の接種でも時間とともに抗体が半減したり、抗体を作ることができない人も報道されています。3回目の接種になったら、それは「しんどいなあ」と思いますねえ。