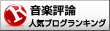2021年5月17日月曜日
本日のCD Aretha Franklin ♪ Live At Fillmore West
2021年5月16日日曜日
本日のCD Aretha Franklin ♪ Spirit In The Dark
反省だなあ ショックです いや恐ろしい
昨日、「四谷いーぐる」のオーナー後藤雅洋氏の書いた本を読んで
「インターネットの普及で誰もが自分の意見を開陳できるようになり、それが文化状況を活性化させた反面、身体経験の伴わない文字情報の氾濫が問題になってきている。ジャズで言えば、ロクに聴き込みもしないで評論家面する輩が増えてきた。」 これは私のことかと忠告を聞いたつもりでありました。
が、その日のSoulive / Turn It Out のレビューでジョンスコが、いつものうねるフレーズでジャムっているのに、ジョン・スコのゲスト参加だが存在感がないとか書いてしまい失態してしまいました。
実は現在の最近のレビューは、このブログで始めたころに結構いい加減に書いていたレビューを書き直している過去記事のリマスターを行っています。だいたい3年前に聴いたアルバムを今、再度聞き直してレビューも更新している感じです。
普段は眠ってしまって聞かなくなってしまった名盤を再度聞いて、自分自身の経年変化も楽しんでいるのですが過去記事をコピペしながら修正するもんで、新しく加えたものと内容がダブっていたり文章のつなぎが変だったりすることはよくありますが、その時の体調や精神状態で、修正がメタメタだったりすることもしばしば。そんな時には見えた後で密かにしまったと思って密かに修正していることも多々あります。
今回は、ジョンスコの参加は2曲だけだったのですが、アルバムの再聞き込みの時におそらく曲を勘違いして聞いてジョンスコは参加していない曲を聴いて、ジョンスコは参加していないぐらい存在感が薄いとしてしまったようです。ジョンスコ・ファンにとってはバカにしているような発言となってしまいツイッターでのご指摘で気づいた次第です。
後藤雅洋氏の「ロクに聴き込みもしないで評論家面する輩が増えてきた」を次の日にやってしまった訳ですから、我ながら、いや恐ろしい💦
このブログは同じアルバムを持っている人に、どんなアルバムだったか懐かしんでもらったり、そんなこともあるのかと聞いたことがないアーチストを聴くきっかけにしていただいたりして欲しいと思ってレビューを書いております。
自分にとっては、記憶力が劣化していく中、音楽体験だけは劣化させたくないのと、ただ単に聴くだけより録音の背景を知って聞いた方がより深く楽しめたり、年代を追ってアルバムを聴いてその変化に驚いてみたり今まで嫌いだった「世界史」を勉強しているような気分でも書いています。
何よりも役に立つのは、自分の所有している音源が把握できるので、CD屋に行ってアルバムをダブって買うミスを防げることです。(防げないこともシバシバ発生はしていますが)
幸いにして面白がって読んでいただける方も徐々に増えてきていますので、それを励みにしております。素人の書くレビューなのですが不適格はあっても、不正確はあってはならないとは思って続けてまいります。
読んでいただいているかた、ご指摘事項ありましたら遠慮せずにこのブログにてコメントいただけると非常にありがたいです_(._.)_
2021年5月15日土曜日
ジャズ喫茶のオヤジは なぜ威張っているのか 後藤雅洋
私が初めて入ったジャズ喫茶は、渋谷のSwing。ジャズ研に所属していた学生の時は足繁くえはないけど「ジャズ喫茶」と言う響きにあこがれて、大人の空間に入って見たくて当時のジャズ研仲間と入り浸りました。Swingでジャズ喫茶を理解した気になっていた私ですが、四谷の「いーぐる」に行ってジャズ喫茶のこだわりや作法を知りました。
ジャズ研ではない先輩に誘われて未だ明るいうちに店内に入るとSwingと同じような空間を想像していた私は暗くないことにびっくり。そして音の良さにびっくりいたしました。リクエスト制度は無く、会話禁止のルールに緊張しておりました。もともと私は音楽はプレイして楽しむタイプなんで楽曲自体を楽しむ人で、音の良さとか再現性などに関心はないのですが「いーぐる」が極上であることは直ぐにわかりました。
そんな思い出のある「四谷いーぐる」のオーナー後藤雅洋氏が30年以上に渡りジャズに携わってこられたジャズ喫茶から見たジャズ感を書かれています。
まだ全部読み切っていませんが、著書の冒頭にこうあります。
「インターネットの普及で誰もが自分の意見を開陳できるようになり、それが文化状況を活性化させた反面、身体経験の伴わない文字情報の氾濫が問題になってきている。ジャズで言えば、ロクに聴き込みもしないで評論家面する輩が増えてきた。」
!!! 私のことか・・ 私のように駄文をブログで綴っているものにとって、きつい忠告分が書かれております。
「威張っているつもりがない」と書かれていますが本の題名が「何故威張っているのか」なんですから、威張っていることは自覚しておられるのは重々承知で相変わらずの紋切り型の辛口コメントに恐縮しつつ、少しづつ楽しみながら読ませていただいています。
2021年5月14日金曜日
本日のCD The Aristcrats ♪ Boing!
2021年5月12日水曜日
本日のCD Lee Morgan ♪ Candy
裏カジノディーラー 田村佳彰
古本屋で常に物色している分野はこのサブカル本。決して我々一般人が踏み入れられない分野の事柄には興味津々であります。普段はカルトやマニアな本が多いのです、今回は「裏カジノディーラー」という直接的なタイトルのサブカルです。
この本を読んでいるとまるでカジノが合法のように錯覚してきますが裏稼業です。何故裏稼業に入ってしまったのか?という部分では普通に就職するような気分で「かっこいい」職業だなと思って入ったという軽いノリで、以降様々な店の開店や経営に携わりプロとしてのプライドをビジネスマン的にもっておられるのが田村さんの凄いとこで、全く警察のお世話にもなっておられないようで、そこらへんも賢い立ち回りをしておられると感心しますが、決して踏み入れてはならない世界であることはよくわかりました。
そしてギャンブルは確実に胴元が儲かる構造で、客は絶対に勝てない構造になっていることも学習できました。(当然胴元が儲からない店は直ぐにつぶれてしまうようで、優秀な従業員を集めなければ潰れる店も多いようなことも書いてあり妙に納得してしまいました)
バカラのルールは良く知りませんが比較的、頭脳戦であるとのことは何かの本で読んだことがありますが毎日やっているディーラーや様々な手口を持っている店にはまず勝てないのはなるほど。
一般人にも読めるように書いてはありますがルーレットやバカラのルールはさっぱりわからず、何が書いてあるかよくわからない箇所もありますが総じて面白く読めました。
一方でいつになったら実現するのかわからない日本の合法カジノについて思うところもあります。裏カジノが成り立つのは先に書いたような手口をカジノが持っているからで、日本のように規制の多い社会では射幸性を気にして規制をしそうです。そんなカジノなんか作ったら潰れる店がいっぱいできるか、面白くもないカジノができてしまうような気がしてなりません。まあ私は競馬などもやらずパチスロと麻雀ぐらいなのでこの世界には足を踏み入れることはないとは思いますが余計な詮索でした。
2021年5月11日火曜日
本日のCD Jaco Pastorius / Live In New York City Vol Two
2021年5月10日月曜日
本日のCD Lihgtnin' Hopkins ♪ Blues Giant Best Selections 3
2021年5月9日日曜日
本日のCD Thelonious Monk / Plays Duke Ellington
ノルウェイの森 村上春樹
今更ながら世界的に有名な作品「ノルウェイの森」を読んでみました。きっかけとしては古本屋で買った「ノルウェイの森と10のオマージュ」というCDブックで、ノルウェイの森をオマージュして書籍の形態でプロデュースした作品で、それほど本の中身の曲に感動してもないのですが、作者の兼松 光氏に、こんな情熱を持たせた原作がどれほどの名作なのか読なければなるまいと思ったわけです。
で読み始めると出だしは青春小説で舞台は昭和の学生紛争の最後のほうでしょうか?淡々とした語り口で、主人公のワタナベトオルくんはドライな現代青年。出だしの直子との思い出は浮遊感のある描写で不思議な雰囲気でありましたが、すぐに昭和でレトロな寮生活の話となり青春小説としてはありかもしれないけど「世界の人がこれに感動するのか?」と上巻の半分以上は疑問を感じながら読み進める。キズキが17歳で自殺したのは主人公の心に残る事件ではあるが彼はドライな感覚なのでそれほど心配はない。しかし直子の入院により何かが変わってきた。ここら辺から話に引き込まれて行き後半の主人公に近い直子と対照的な緑が存在感を強めてきてぐっと引き込まれる。感情はあまり露わにしないワタナベくんが苦悩することにももどかしくも、共感するものがある。
全体的には小説にありがちなパターンの伏線や仕掛けはなく、淡々と物静かに描かれているが。生きていれば必ず「喪失」はあって自然なことであり受け入れなけば人は生きていけないことを訴えるでもなく淡々と描いている青春、恋愛小説でありました。いきつけの「おでんバー」で常連さんやマスターと音楽や本、芸術の話題は多いので、この本のことも話題にしました。昔読んだことがある人も多かったのですが中身については忘れて思い出せない人が100%だったのは相当昔の作品であったせいか?割と平坦な感じのする作品だからか?印象的には薄い小説ではありますが10年後ぐらいに再読してみたい作品ではあります。私は覚えているんでしょうか?どんな気持ちでこれを読めるのか?気になる作品ではあります。
作品中にでてくるノルウェイの森も直ぐには頭の中には浮かばないけど聞けば思い出せる曲という私にとっては印象の薄い楽曲
作品中「ドイツ語の授業が終わると我々は新宿の街に出て、紀伊國屋の裏手の地下にあるDUGに入ってウォッカ・トニックを二杯ずつ飲んだ。」のくだり我々日本人のジャズ・ファンにはこれだけでくすぐるところでもあります。(海外の方にはわからないと思いますが)
CDとレコード
私は音楽好きではありますがレコードプレイヤーは所有しておらずCDをPCのハードディスクに落としながらライブリを作成して、PCをプレイヤーにしてスピーカーはPCとは別にのもので聞くとか、Walk Man に落として聴くなどで楽しんでいます。
住居環境が借家のマンションであるため、大音量で聞くこともできないので再生や音質にはこだわらずに楽曲を楽しむようにしているのですが、いきつけの「おでんバー」のちゃんとしたオーディオで聴くと同じ曲でも自宅では気づかなかった音が聞き取れたり臨場感が違うことは理解しているのですが、PCに落とした音源でもちゃんとした機器で聴けばそれほど大した差はないだろうと思っていました。
ノエルカレフの「死刑台のエレベーター」を本で読みながら、マイルスのサントラを家で聴いていたら、マイルスがちっとも面白くなくて Walk Man に落とした音源を「おでんバー」のちゃんとしたオーディオで聴いたら全く違って聞こえて繰り返し聴くほどに印象が変わり、音楽用の録音機器なら良い音で保存できるのはさすが世界の Walk Man と思ったこともありました。一方で私が購入したサルサのCDを「おでんバー」のマスターが気にいって店のPCのハードディスクに録音して後で聴いたらCDの方が音質が良くてPCなどによってはハードディスクのデータでは音質が劣化するのかと気づいたこともあります。
最近びっくりしたのはジョニ・ミッチェルのアルバム「Shadows and Light」。購入したCDを「おでんバー」で聴いたらマスターが「これはレコードで持ってるよ」とCDをかけ終わった後にレコードを聴いたらレコードの方が臨場感があって全く違って聞こえます。こういった聴き比べはマスターもしたことがなくて驚きだったようです。
ちなみにこの時普通に音楽を聴くけどそれほどこだわりの無い常連さんが同席されていてマスターと私のはしゃぎっぷりに不思議な顔をされています。違いは歴然としているとマスターと私は聴き分けていたのですが彼にとっては同じ音で、この違いが全く聴き分けられないようでした。人間による感性の違いにも、また驚きでした。この世界深いですね。