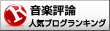長年マイルス作品をプロデュースしてきたコロンビアのTeo Maceroと別れ、1984年に発表したマイルスのセルフ・プロデュース体制でレコーディングされたスタジオアルバム。マイルス復活後第4作目。マイルスが向かおうとしていたエレクトリック・ファンクの方向性が明確化された作品で、本作よりベースの Darryl Jones(ダリル・ジョーンズ)がマイルスのグループに正式加入しました。彼はこの時点ではシカゴで活動していたローカルなミュージシャンに過ぎなかったが、シンセの Robert Irving III, そのバンド仲間でマイルスの甥であるドラマーの Vince Wilburn Jr. の推移によりニューヨークの2700席クラスのコンサートホール、エイブリー・フィッシャー・ホールへの参加が要請されたとのことで、それまで数百人程度のディスコ、ライブハウスでの演奏しかしていなかったのでビビッたらしい。ちなみにこのコンサートホール、金管楽器が鳴りすぎ、低音が弱いとの評価でクラシック・ミュージシャンからは評判が悪く後に音響改修されることになったらしいので電化マイルスバンドには丁度良かったのでしょう。
他、このアルバムには ソプラノサックスでBill Evans 、Branford Marsalis、先ほど紹介のRobert Irving III、ギターに John Scofield(g)、ベースは先ほど紹介の初参加 Darryl Jones、ドラムに Al Fosterm、パーカッションは Mino Cinelu が参加していて、Branford Marsalisをレギュラー・メンバーに起用しようと考えていましたが、それは実現できませんでした。
それではレビューしていきます。Decoy シンセの Robert Irving III作品、ファンクっぽいけどジャズ・ファンクではない楽曲です。いわゆる売れ線的なリフとリズムとなっています。Robot 415 は1分10秒の実験的な感じがする曲で、シンセとパーカッションにワウのエフェクトがかかったトランペット。Code M.D. は、かなりファンクも入っていないフュージョン作品です。John Scofield のギターは、あまりウネウネしていないですね。マイルスも、あの音を探しながら吹くような感じの吹き方です。Branford Marsalisも参加ですが、デスクトップで作ったってイメージで、軽いですかね。Freaky Deaky はマイルス作曲で、シンセを担当でトランペットは吹いていません。これも抽象的で実験的な曲となっており緊張感とかは全くないヒーリングのような曲ですね。What It Is は、1983年7月7日、マイルス・バンドがモントリオール・ジャズ・フェスティバル出演時の録音です。かなりのファンクなフュージョンで。マイルスとジョン・スコフィールドの共作で、売れ線です。That’s Right は、アレンジにギル・エヴァンスのマイルスとジョン・スコフィールドの共作。本作はかなり、ゆっくりしたテンポで、どこかのソウル・ナンバーのオマージュかと思う曲です。That’s What Happend 実は前作 Star People の Speak と同じ曲とのことですが、前作は、かなりロック的な感じで、今作はファンクな感じ。前作のテーマらしきものは今作に反映させていないと思われ、同じ曲とはAIでも判別はできないものと思われます。これもマイルスとジョン・スコフィールドの共作。
ロックに近い路線もあったが、よりファンクに寄せてきた実験作のような感じです。大衆受けを狙ったかと言えばそうでもない。アルバムのまとまりも無いような気もするし、、、うーん。面白くはあるかなあ🎶
producer : Miles Davis
recorded by : Guy Charbonneau
recorded at Record Plant Studios, N.Y.C.
Track 4 Recorded at A&R Studios, N.Y.C.
Track 5 Recorded Live at Festival International De Jazz De Montreal
1. Decoy (Robert Irving III)
trumpet : Miles Davis
synthesizer, drum programming (electric) : Robert Irving III
electric bass : Darryl "The Munch" Jones
guitar : John Scofield
drums : Al Foster
percussion : Mino Cinelu
soprano sax : Branford Marsalis
2. Robot 415 (Miles Davis, Robert Irving III)
trumpet, synthesizer : Miles Davis
synthesizer, synthesizer (bass), drum programming (electric) : Robert Irving III
percussion : Mino Cinelu
3. Code M.D. (Robert Irving III)
trumpet : Miles Davis
synthesizer, drum programming (electric) : Robert Irving III
electric bass : Darryl "The Munch" Jones
guitar : John Scofield
drums : Al Foster
percussion : Mino Cinelu
soprano sax : Branford Marsalis
4. Freaky (Miles Davis)
synthesizer : Miles Davis
electric bass : Darryl "The Munch" Jones
drums : Al Foster
percussion : Mino Cinelu
5. What It Is (Jhon Scofield, Miles Davis)
trumpet, synthesizer : Miles Davis
guitar : John Scofield
electric bass : Darryl "The Munch" Jones
drums : Al Foster
percussion : Mino Cinelu
soprano sax : Bill Evans
6. That's Right (Jhon Scofield, Miles Davis)
trumpet, synthesizer : Miles Davis
synthesizer : Robert Irving III
guitar : John Scofield
electric bass : Darryl "The Munch" Jones
drums : Al Foster
percussion : Mino Cinelu
soprano sax : Branford Marsalis
7. That's What Happened (Jhon Scofield, Miles Davis)
trumpet, synthesizer : Miles Davis
guitar : John Scofield
electric bass : Darryl "The Munch" Jones*
drums : Al Foster
percussion : Mino Cinelu
soprano sax : Bill Evans
▶ Decoy