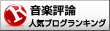マイルスは、Miles In The Sky でエレクトリック化していくのですが、Miles In The Sky の録音は1968年1月5月。Miles In The Sky からハンコック、ロン・カーターが参加し、レコーディングでは限定的にエレクトリック・ピアノ、エレクトリック・ベースを使っており Miles In The Sky 録音以降のライブではアコースティック楽器を使いレパートリーは従来と同じだったそうです。そしてこのアルバムは、その直後の1968年6月19・20・21日の録音で、ハンコックはエレクトリック・ピアノ、ロン・カーターはエレクトリック・ベースを取り入れることとなります。その録音がギル・エバンスとの共作 3. Petits Machins (Little Stuff) で、2. Tout De Suite、4. Filles De Kilimanjaro はマイルスの単独作となります。
作曲の側面でマイルスの流れを見ると、マイルスはメンバーに演奏、楽曲提供させながら成長を促していく方針をとり、マイルスの作曲は E.S.P. では4曲、Miles Smiles では1曲、Nefertitiではゼロになっていたのが、このアルバムでは作曲はなんと全てマイルスになっています。なお、このアルバムでも重要な役割を果たすメンバーのウェイン・ショーターが2023年3月2日89歳でロサンゼルスで亡くなりましたので、マイルス・バンドへの加入後のアルバムを列記しておきます。E. S. P. 、Miles Smiles、Sorcerer、Nefertiti、Miles In The Sky 、Filles De Kilimanjaro、In A Silent Way。
ものすごく面倒なアルバム作成の背景を書いてしまいました。面倒なことを考えずに音を聴けば良いと思っていたものの、この作業が最近楽しくなってきているのが、段々と歳をとってきた証拠ですね。
一聴すると地味に聞こえる本アルバムではありますが、アルバム制作の背景、メンバーを知ってから聴くと、ファンクとエレクトリックに照準を合わせ始めた作品として中々濃いアルバムに聞こえてきます。
さて、そろそろレビューします。Frelon Brun 最初に聴いた時には印象が薄かったのですが、確かにロック、ファンクに近づく作品として聴くと、かなりロック的なトニー・ウイリアムスのドラムから始まり、ファンク的ではありますが手探りで状態のように聞こえるアコースティックベースとピアノにマイルスが切り込んでいく、ショーターも切り込んでいくが何か勝手が違うように聞こえる。ピアノも色々なフレーズを試してファンクの色を出しながら自分なりの正解を探しているように聞こえる。それでもまとまってしますのが凄いなるほどの出だし。Tout De Suite では、音数少な目になるがグッとバンドの音のまとまりが出てきたように感じます。ドラムはジャズよりで、ベースは余計なことはしない。リズムではなく低音の単発で曲を支えているため他のメンバーの自由度が増しているように聴こえます。ピアノはハンコックに交代でチックコリアよりメロディアスになって曲に柔らかさを与えているように感じます。Petits Machins (Little Stuff) は楽器はエレクトリックであるけどアコースティックな響きに戻ってきました。いや曲が進めばそうでもないか。エレクトリックな楽器の音の粒立ちの良さをうまく使ったピアノに変わってきているのかな。Filles De Kilimanjaro はタイトル曲で確かに地味だけど曲としてまとまっています。単調で動かないベースラインはマイルスの指示なんだろうけど狙いすぎも感じます。 Mademoiselle Mabry (Miss Mabry) こちらは雰囲気のある曲でビロードに包まれているようなゴージャスな感じがします。マイルスも気持ちが入っているし、ショーターのサックスも曲を良くとらえている感じがします。Tout De Suite (alternate) は、ボーナストラック。
先にも書きましたが地味だけどクインテットで進めていたアプローチにエレクトリックを導入した経緯の知識を得てから聴くのと、素の状態で聴くのは大違いの印象の完成度のあるアルバムでした。
trumpet, leader (directions in music) : Miles Davis
electric piano : Chick Corea (1, 5), Herbie Hancock (2-4, 6)
electric bass : Dave Holland (1, 5),
acoustic bass : Ron Carter (2-4, 6)
drums : Tony Williams
tenor sax : Wayne Shorter
producer : Teo Macero
written by M. Davis
Track 1, 5, 6 recorded 9/24/68, New York
Track 2 recorded 6/20/68, New York
Track 3 recorded 6/19/68, New York
Track 4 recorded 6/21/68, New York
1. Frelon Brun
2. Tout De Suite
3. Petits Machins (Little Stuff)
4. Filles De Kilimanjaro
5. Mademoiselle Mabry (Miss Mabry)
6. Tout De Suite (alternate)