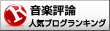1993年リリースで、ジミヘンのプロデューサー・エンジニアだった Eddie Kramer の発案から製作されたジミヘンのトリビュート・アルバムです。Eddie Kramer は南アフリカ生まれですが、19歳の時にロックが流行り出した60年代初期のイギリスに移住。レコーディング・プロデューサー/エンジニアとして、ビートルズ、デヴィッド・ボウイ、エリック・クラプトン、ジミ・ヘンドリックス、キンクス、KISS、レッド・ツェッペリン、ストーンズ、サンタナ、ピーター・フランプトン、ホワイトスネイクなど、かなりの大物のコラボレーターを務めておられる凄い人です。
ジミヘンは音楽のジャンルを問わずに、様々な影響を与えたミュージシャンです。このトリビュートにも様々なジャンルの人が参加しています。だからジミヘンの曲をやってもジャンルを超えた個性がでるもので、演奏者によってこのジミ・ヘンの曲が全く別物に生まれ変わっています。ロックやブルースのミュージシャンは直接的に音やコード遣いが影響を受けるのは容易に想像を受けますが、パット・メセニーもやっぱり聴いてたんだと言うこともわかり、メセニーらしからぬロック的ギターにビックリしたりニヤリとします。そういった意味でも中々の濃い内容のトリビュートであると思います。
ジミヘンはみんな好き・・でも時代は変わるし音楽も変化していきます。これは名盤ではないが演奏している人が楽しんでいるし、聞いている私たちもニヤっと楽しめるヤツです。既に廃盤みたいですが、中古盤店などでたまにお手ごろ価格で見かけます。是非聞いてみてニヤッとしていただきたい🎵
1. Purple Haze / The Cure
vocals : Robert Smith
guitar : Perry Bamonte, Robert Smith
keyboards : Perry Bamonte
bass : Simon Gallup
drums : Boris Williams
2. Stone Free / Eric Clapton
vocals : Eric Clapton
backing vocals : UNV
guitar : Eric Clapton, Nile Rodgers
keyboards : Richard Hilton
bass : Bernard Edwards
drums : Tony Thompson
3. Spanish Castle Magic / Spin Doctors
vocals : Chris Barron
guitar : Eric Schenkman
bass : Mark White (2)
drums : Aaron Comess
4. Red House / Buddy Guy
guitar, vocals : Buddy Guy
piano : Johnnie Johnson
bass : Billy Cox
drums : Ray Allison
5. Hey Joe / Body Count
Bass : Mooseman
Drums : Beatmaster "V"
Guitar : D-Roc (3), Ernie C
Lead Vocals : Ice-T
Mixed By : Michael White (4)
Producer : Ernie C
6. Manic Depression / Seal & Jeff Beck
vocals : Seal
guitar : Jeff Beck
bass : Pino Paladino
drums : Jimmy Copley
7. Fire / Nigel Kennedy
acoustic guitar, guitar (Bottleneck) : Sagat Guirey
guitar : John Etheridge
bass : Rory McFarlane
drums : Rupert Brown
cello : Caroline Dale
viola (acoustic), violin (phased), violin (kerrang), piano (doctored) : Nigel Kennedy
8. Bold As Love / Pretenders
mixed by : Bob Clearmountain
9. You Got Me Floatin' / P.M. Dawn
guitar : Herbie Tribino
10. I Don't Live Today / Slash & Paul Rodgers With The Band Of Gypsys
vocals : Paul Rodgers
guitar : Slash
bass : Billy Cox
drums : Buddy Miles
11. Are You Experienced? / Belly
Vocals : Gail Greenwood, Tanya Donelly
Bass : Gail Greenwood
Drums, Percussion : Chris Gorman
Guitar : Tanya Donelly, Thomas Gorman
\
12. Crosstown Traffic / Living Colour
lead vocals : Corey Glover
vocals : Doug Wimbish, Will Calhoun
guitar : Vernon Reid
bass : Doug Wimbish
drums, piano, whistle (Kazoo) : Will Calhoun
13. Third Stone From The Sun / Pat Metheny
guitar, bass, keyboards, programmed by, synthesizer (Synclavier) : Pat Metheny
bass : Jaco Pastorius, Matthew Garrison
drums (additional) : Jack DeJohnette
14. Hey Baby (Land Of The New Rising Sun)/ M.A.C.C
vocals : Chris Cornell
guitar : Mike McCready
bass : Jeff Ament
drums : Matt Cameron