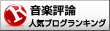時空を超えてどこかに行ってしまいそうな楽曲が多いエスペランザですが、これは大丈夫。ジャズをベースにリラックスできて、かつ彼女の中にある独特の音階も楽しめるのでジャズ好きのエスペランザ初心者なら入門編としてお勧めです。普段はポップな音楽を好まれている方の初心者入門は売れたアルバムの Radio Music Society ですね。
エスペランザは史上最年少の20歳で、バークリー音学院の講師に就任したベース・プレイヤーであり、ソング・ライターであり、ボーカリストであります。ルーツとしては、アフリカ系アメリカ人、ウェールズ及びスペインの血を引いているとのこと。ベース・プレイヤーとしても高い技術がありますが、ジャズ、ポップス等のジャンルに寄せた曲も素晴らしいですが、その曲の中に見える彼女の独特の音階やリズムが凄いのと、ジャンル分け出来ない音楽も一聴すると訳がわからないのですがファンになると、それが高い芸術性を持っているように聞こえる訳です。ボーカルも非常に透明感があり的確に複雑な音程の中を泳ぐように歌います。イブとかは見たこと無いですけど、どうやら私はすっかりエスペランザのファンになってしまっているようで、はるか前に降参しております。ライナー・ノーツの手書きの字までアートですから。
さて、このアルバム、エスペランザのセカンドで2008年リリースです。本年は2023年になってしまいましたので約14年前のアルバムですか、いつのまにか懐かしのアルバムになってしまいました。
再度拝聴しましょう。Ponta De Areia はイントロでアフリカンな響きなようで浮遊感のあるコーラスで始まりますがイントロが終わるとポップスのようなボーカルのメロディーラインになりクルクルと展開していくジャズ・フォーマットですが最後はポップスのように聴きやすいメロディーでいきなりノックアウトですね。I Know You Know は、ゴツゴツしたベース・ラインから始まるのですが、ここでアコースティック・ベースなのに粒だちの良い発音と滑らかな音にベーシストとして本物がここにいることが実感できます。拍子の数え方はよくわかりませんが、おそらく6拍子でしょうか。この拍子がぐるぐると音の波が押し寄せるような効果があってまた気持ち良い。Fall In は静かな曲です。エスペランザの曲でバラードというのは何か当てはまらないような気がするので静かな曲と表現しました。中域を活かした伸びやかなボーカルが心に響く美しい曲です。I Adore You は、アフリカンな響きのあるスキャットで1曲目と同様にポップス、ワールドミュージック、ジャズのような要素が目まぐるしく1曲の中で変わっていきます。ピアノ・ソロの時はジャズ・フォーマットでの演奏でのアドリブですが続くベース・ソロ部分(おそらく)はエスペランザはフォーマットはお構いなしでの演奏で格が違います。Adore は憧れる、熱愛するということだそうです。Cuerpo Y Alma はスタンダード Body & Soul ですが、ここはエスペランザはスペイン語で歌っています。語感の違いが情熱的な印象を持たせてくれるのが面白いですね。変拍子っぽいところを入れていることはありますが珍しく変則技があまりない完全にジャズですね。She Got To You では、フュージョンぽい出だしで出だしの表情はあまり変えずに曲が進行します。これは聴きやすい。ですが面白くはないかな。ライブでは盛り上がりそうです。Precious は、可愛らしいメロディーで、このアルバムで一番印象に残るメロディーラインです。惚れます。Mela は、ザ・ジャズって感じです。普通にジャズです。ソロなんかは凄いクオリティ高いんだけど、エスペランザのアルバムの中では面白みにかけるような気がしてしまうのが困ったもんです。Love In Time は、曲名通り甘い感じです。ディナー・ショーとかでかかるようなゴージャス感もあります。Espera は当然自分の名前から曲名をとったんだろう曲です。自分の存在を確認するような歌詞と我々普通の人に安心感を与えてくれる曲の進行でこれも良いですね。If That's True は、8ビートのドラムから始まり4ビートに変化したりする曲でメンバーのセッションのような曲です。なかなかスリリング。Samba Em Preludio でアルバムは終了します。バド・パウエルの曲のようですがボーカルがまたスペイン語になっています。このしっとりエスペランザも良いですね。ずっと愛聴します。
bass : Esperanza Spalding
vocals : Esperanza Spalding (1 to 10, 12)
piano : Leo Genovese (1 to 11)
guitar : Niño Josele (12)
drums : Horacio Hernández "El Negro"(4, 6, 8), Otis Brown (1, 2, 5, 7, 9 to 11)
bongos : Jamey Haddad (1, 2, 6)
percussion : Jamey Haddad (4, 10)
backing vocals : Gretchen Parlato (1, 4), Otis Brown (4, 7), Theresa Perez (4)
alto sax: Donald Harrison (6, 11)
trumpet : Ambrose Akinmusire (8, 11)
1. Ponta De Areia
2. I Know You Know
3. Fall In
4. I Adore You
5. Cuerpo Y Alma (Body & Soul)
6. She Got To You
7. Precious
8. Mela
9. Love In Time
10. Espera
11. If That's True
12. Samba Em Preludio
▶ Precious
▶ Espera