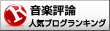1958年録音の作品でワンホーン・カルテットでの録音はこれだけ。なんといっても芸術的にどうだとか、あのソロが良いとかいうのとは別の次元の、実にイキな演奏はやっぱり良い。これは他のも聞かなければいかんと思い、この作品を皮切りにその後色々な作品を聴いてきました。Candy 1957、Leeway 1960、The Sidewinder 1964、 Sonic Boom 1967
とにかくトランペットの発音が品行方正でメロディも含めてダンディな響きで、この録音時はまだ19歳だったということにもかなりの驚きです。ティーンにして、このダンディズムにはおそれいります。全体の構成は軽く軽快であり聞きやすくて平坦でありながらクオリティが平均的に高いので、落ち着いた気分で本を片手に珈琲を飲みながらといったシチュエーションが似合うアルバムではないでしょうか。
それでは、作品全体をレビューしていきましょう。Candy 甘いメロディーで明るいラブソングです。色々な人に演奏されている曲ですが、1956年の Nat King Cole が、有名なところです。ボーカルものと比較にはならないですが、Lee Morgan のこのバージョンは、後にも愛される名演と言える出来だと思います。2分49秒のトランペット・ソロの出だし4分17秒の違和感も、誰もマネできない天才的なアイデアと感心します。Since I Fell For You 先輩たち Sonny Clark トリオの素晴らしい後押しで、この胴の入った演奏ができるのか、先輩たちに負けてられるかとの演奏なのか、端正な音使いでのトランペット・ソロです。目立ち過ぎずに、これまた、いぶし銀のピアノが実に心地よいです。 C.T.A. は、テナー奏者 Jimmy Heath の作曲した曲です。こういった早いバップは聴いてい楽しい。All The Way は、1957年の映画 The Joker Is Wild (最近のホラーのヤツではありません)の主題歌で、ここら辺は当時の流行りを意識の曲ですが、A&M の誰かの作品群のように商業的で軽くはなく、抒情的に丁寧に作られています。ありです。Who Do You Love I Hope これも映画アニーよ銃をとれの主題歌ですが、実に明るいトランペットのソロが映える良い曲。Personality は、1940年代のポピュラー・ソングで、丁寧なトランペットがテーマ部分でバンドを牽引し、ソロからガラッと表情を変えて雄弁になる対比も素晴らしい。決して若造の吹くトランペットでは無いものが感じられます。All At Once You Love Her リイシュー盤につくボーナストラックです。スリリングな名演が付け加えられています。
多作な人なのでこの後も多くの作品を残していますが、この頃のLee Morganの状況を見ていたら、前年の18歳でDizzy Gillespie のビッグバンドに参加していました。しかし直ぐに解散、またコルトレーンのBlue Train への参加、Art Blakey のメッセンジャーズへの参加し Moanin ' のレコーディングなどがあります。1957年’58年はミュージシャンの起点となる大事な年であったようです。じっくりと聞きながら「ああジャズっていいな」ってストレートに誰もが感じられるおススメです🎶
trumpet : Lee Morgan
piano : Sonny Clark
bass : Doug Watkins
drums : Art Taylor
producer : Alfred Lion
recorded by : Rudy Van Gelder
recorded at Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey on November 18, 1957 (#2, 6 & 7) and February 2, 1958 (#1, 3 to 5)
tracks 1-6 originally issued in 1958 as Blue Note BLP 1590.
#7 is a bonus track (not part of original LP) originally issued in 1987 on the first CD issue of this album
1. Candy / Alex Kramer, Joan Whitney, Mack David
2. Since I Fell For You / Buddy Johnson
3. C.T.A. / Jimmy Heath
4. All The Way / Sammy Cahn & Jimmy Van Heusen
5. Who Do You Love I Hope / Irving Berlin
6. Personality / Jimmy Van Heusen And Johnny Burke
7. All At Once You Love Her / Rodgers & Hammerstein
▶ Candy
▶ C.T.A.