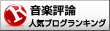これは、発売されて直ぐに購入したアルバムです。チキン・シャックは学生の時にサックスの先輩がよく聴いていたバンドで私自体は思い入れがあるバンドでは無いのですが、つられて聴くうちに心地よいバンドであることは知っていましたし、ギターの 山岸潤史 も日本のフュージョン界では重要な位置を占める方で、耳にすることは多かったので23年ぶりの発売と聴いて、まず間違いはないものと確信しての購入でした。
すっかり歳をとってしまわれたメンバーは、土岐英史(sax)、山岸潤史(g)、続木徹(key) で、結成は1986年でした。前作は1990年に発表の CHICKENSHACK VI で、23年ぶりの2013年の発売で、10作目となります。昔はもっとネチッとしたサウンドでクロスオーバーとブラコン的な要素が強かったのが、今回は軽めになったソウル、R&B系フュージョンで円熟味を増した演奏に変化していると感じます。
さてレビューです。Have Yourself a Merry Little Christmas は、クリスマス・ソング。発売日は2013/06/12です。?と思っていると、どうやら'91年のChickenshackのライブ盤で Prime Time の最後の曲です。この盤がベスト盤やコンピ盤、リユニオン盤を除けば実質的なラストアルバムになるので、その続きという訳ですね。続くは Flow は歌物です。歌詞は Wornell Jones 作曲は 続木徹 と書いてあるのでこのアルバムのための書下ろしのようです。Go は 山岸潤史 の作曲のゆったりとしたフュージョンでトリッキーなこともなく落ち着いて聴ける聴きやすい曲で各自のソロも取りやすい進行です。ギターソロの音使いは私のツボに入る感じ。It’s Rainin’ on my Heart は、土岐英史の作曲のブルース。それも泥臭いヤツです。こんな曲はこのメンバーなら何にも考えずに手癖のみで演奏でしょう。王道すぎて楽しい。October Sky は山岸潤史で、アースのセプテンバーがモチーフですね。だから曲名もオクトーバーと納得。私の世代の人は嬉しい楽曲ではないでしょうか。You Make me Feel Brand New は、スタイリスティクスですねえ。山岸さんの趣味でしょうか。Thrill ain’t Gone (we’re still together) は、続木徹の作曲で王道のコード進行と構成で Fourplay が好きな人にはばっちりです。Have You met Johnny G ? は、また土岐英史の作曲。Johnny G とは、Johnny ''Guitar'' Watson のことでしょうか。The Gadd Gang っぽい楽曲です。ピアノは Richard Tee、ギターは Cornell Dupree に随所でなりきってます。Christmas Time is Here は、Vince Guaraldi Trio の Charlie Brown の Christmas アルバムでは子供たちが合唱している曲です。渋い選曲かな。最後の Walk Alone は山岸潤史で締めくくりです。モチーフは Peple Get Ready ですよね。もしかしたらコード進行だけかもしれませんが、メロディだけ女性ボーカルを入れてきたり、ジェフベックみたいな音を入れてきたりと確信犯だとは思います。こういった遊び心が随所に入っているのも熟練されたミュージシャンの余裕を感じますね🎵良きアルバム。
【オリジナルメンバー】
sax : 土岐英史
guitar : 山岸潤史
keyboads : 続木徹
【ゲスト】
bass : 清水興、Wornell Jones
drums : 鶴谷智生、Fuyu
1. Have Yourself a Merry Little Christmas
2. Flow
3. Go
4. It’s Rainin’ on my Heart
5. October Sky
6. You Make me Feel Brand New
7. Thrill ain’t Gone (we’re still together)
8. Have You met Johnny G ?
9. Christmas Time is Here
10. Walk Alone
▶ Flow