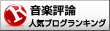Sonny Clark は1931年生まれのピアニストで1963年に1月13日、ヘロインの過剰摂取により31歳で亡くなっています。地味なスタイルのせいか本国アメリカでは全く売れず知名度がないのに日本では人気のピアニストとのこと。また他の説では、麻薬常習者のためキャバレーカードが発行されずジャズ・クラブでの演奏が出来なかったため知名度が無かったという説もあります。しかしサイドマンとしては、1954年1月、Billy Holiday のケルン公演、 Lee Morgan / Candy(1958)、や Dexter Gordon / Go! 等にも参加しています。
本作は、New York Times 紙は「いつまでも残るハードバップのクラシック (enduring hard-bop classic) と評されているとのことで、少々古臭い曲調ではあります。Cool Struttin'は(気取って歩く)の意味で、Francis Wolff という人が撮っておられますジャケットのセンスは非常に良いと思います。日本のジャズ喫茶史上最も多くプレイされたアルバムの一枚でとも言われております。確かに、いかにもわかりやすいインパクトのある1曲目はジャズ喫茶でかかれば、心して聴く構えが出来る曲でアルバムをセレクトする側としては重宝するものであったことが予想されと思っていたら、ジャズ喫茶「メグ」のオーナー寺島靖国氏の著書「ジャズの聴き方に法則はない」には、真逆の記述がありました。Art Blakey / Moanin'、Mal Waldron / Left Alone なんかは1日にリクエストが何回もかかり「ヒット・パレード」物と称して差別待遇をして当時は「さっきかかった」「盤に傷がついた」などと称して断っていたことがあるとのこと。なるほどヒットし過ぎるとそうなのかと納得し、何かに似ていると思ったら Moanin' の印象と似ているのかと納得。
本盤は参加メンバーも有名どころが揃っています。Sonny Clark(p)、Art Farmer(tp)、Jackie McLean(as)、Paul Chambers(b)、Philly Joe Jones(ds)が参加しているところを確認しレビューです。
オープニングはタイトルトラックの Cool Struttin' で、ジャケットの女性がカッカッと気取って歩いている様かと思うと古臭いと思われるテーマもクールに聴こえてくる。時代が時代なら違った聴こえかたをしたに違いありません。ソロでは Art Farmer がいかにもブルースな演奏をして Jackie McLean がブイブイ言わせ、弓ベースのソロもまとまっています。Clark はリーダーで目立ちすぎるということも無く程よいアンサンブル。次は、Cool Struttin' と同じく Clark のオリジナル・ナンバーの Blue Minor。ブルージーで親しみやすいメロディーでありながら途中のテーマ部分のラテン・アレンジも魅力的で、McLeanとFarmer は伸びやかにソロを撮っています。1曲目より Clark は存在感があり粋がった感じのピアノがとても良い。Sippin’ At Bells は、小気味よいドラムソロのイントロと管2本のポップで印象的なテーマ。聴く人が聞くとバド・パウエルの影響があるらしいスタイルらしいが私には未だそこを聴きとる力はなく、ただただ軽やかな推進力のあるスイング感が好き。そして Deep Night で仕上げです。My Funny Valentine の作者として有名な Lorenz Hart / Richard Rodgers の作品で、非常にかっこよい曲で Clark のピアノ がとても粋な感じにキマっています。
全体的にアルバム全体の曲の構成、長さ、王道で潔い演奏は、聴きやすく黒く煮詰めた珈琲と薄暗い空間が良く似合うアルバムですね🎵
piano : Sonny Clark
bass : Paul Chambers
drums : "Philly" Joe Jones
alto sax : Jackie McLean
trumpet : Art Farmer
producer : Alfred Lion
recorded by : Rudy Van Gelder
recorded on January 5, 1958. Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey
1. Cool Struttin'
2. Blue Minor
3. Sippin' At Bells
4. Deep Night