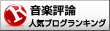Monk が Bud Powell のヘロンイン所持を庇ってキャバレーカードを没収されたのが1951年、その後NYエリアでの演奏活動が出来ずにいたが、マネージャーの Harry Colomby と ニカ夫人の尽力で1957年に奪回し、NYでの活動を再開し、Coltrane と1957年7月18日から12月26日までマンハッタンの Five Spot で活動することになります。その1958年のニューヨークの Five Spot Cafe でのライブ録音がこのアルバム。同じショーの録音が Thelonious in Action として発売されています(残念ながら持ってません)。また、恐ろしく音の悪い未発表音源の The Thelonious Monk Quartet Featuring John Coltrane / Live at the Five Spot Discovery! (1957) も後に発売されています。この時代それほど当たり前に、このクラスのジャズ・アーチストのライブが身近に聞けたということで、これだけ凄い演奏なのに酒を飲んで騒いでいる客がいます。私もこんなライブ聞きながら騒ぎながら酔っ払ってみたいです。
なお、ジャケットはイタリアの画家 Giorgio De Chirico(キリコ)の作品です。後のシュルレアリスムに大きな影響を与えた画家だそうです。「口頭、記述、その他のあらゆる方法によって、思考の真の動きを表現しようとする純粋な心的オートマティスム。理性による監視をすべて排除し、美的・道徳的なすべての先入見から離れた、思考の書き取りを定義し、シュルレアリスムはジークムント・フロイトの精神分析とカール・マルクスの革命思想を思想的基盤とし、無意識の探求・表出による人間の全体性の回復を目指した」という難解な定義と歴史があるようですが、日本では1930年以降はブルトンが提唱した無意識の探求という本来の目的から離れ、「現実離れした奇抜で幻想的な芸術」という意味で「シュール」という日本独自の概念・表現が生まれることになったそうです。
1957年に Five Spot へ復帰したメンバーは、サックスが John Coltrane、ベースがAhmed Abdul-Malik ドラムが Shadow Wilson この1958年では サックスが Johnny Griffin へ、ドラムが Roy Haynes へと変わっています。
1957年のセッションでは John Coltrane の奔放さがあるため、モンクがリズムキープに回り気味のバランスだったような気がしますが、本アルバムでは Johnny Griffin のテナーとピアノの掛け合いの具合がちょうどよい気がします。録音によってモンク臭さの度合いが違うと思うのですが、これはモンク臭さがかなり出ていると思います。
全曲レビューです。「Nutty」モンクの先導でテーマが始まるモンクらしい音が詰まっています。グリフィンのソロが始まったときは、モンクがリズムをきっちりと入れて伴走し、佳境になると、今度は音量も抑えめのコードを少し抑えるだけにしてドラムとベースに先導役を任せる。そこからピアノソロでは 自分の色を出しまくりながら、きっちりとスイング。 「Blues Five Spot」ブルース・セッションになります。聴きどころは Johnny Griffin を一人だけ置き去りの長めのソロかと思います。ソロの後の客のやる気のない拍手は少し残念。ベースソロまで行くと客の手拍子が少し聞こえます。ソロ回しの後のテーマに戻ると、モンクが最初だけ、エコーのようにフレーズを重ね、以降もやるのかなと期待していると通常運転の面白い仕掛けもあります。「Let's Cool One」これも他愛もないメロディーのテーマですが、モンクだと直ぐにわかる楽曲。優しい響きのコード進行に身を任せての、各自の伸びやかなソロが楽しいです。モンクも Johnny Griffin のソロで楽し気に弾きながら歌っているのが聞こえます。そしてまた Johnny Griffin を一人だけ置き去りのソロですが、2曲目より更に長い超ロングソロで、今度は客の拍手はヤンヤになってきて良い雰囲気。当然続くモンクのソロもノリノリになるのは当然です。最後の〆の息もピッタリ。In Walked Bud このBud Powell のことでしょうか。珍しくモンク節ではない正調スイングのモンク曲です。Bud Powell は、50年代中期以降は麻薬やアルコールなどの中毒に苦しみ、精神障害(統合失調症を負ていたので、その励ましの曲かと思われます。Just A Gigol 本アルバムの中で唯一のモンク以外の作曲者の曲となりますが、しっかりモンク節を入れているピアノ・ソロです。ライブでしんみりするところですね。短いながらも味わい深い演奏です。「Misterioso」 非常に簡単な旋律でありながら、幾何学模様のように音が散りばめられている、印象が強烈なタイトル曲「Misterioso」あまりに印象的すぎて一度聴いたら忘れられないヤツです。この曲の Johnny Griffin も吹きすぎず、引っ込み過ぎず、非常に良い味を出してます。モンクのソロ中の休み時間は非常に長いですが、Johnny Griffin のソロに聞き入っているのでしょう。合間合間でウーと掛け声を入れてくるところがあります。モンクも、その後雄弁に語るかのような長尺のピアノ・ソロで、なるほどテーマ曲にした貫録の演奏です。「 'Round Midnight 」モンクの代表曲の一つで、モンクの曲の中でも後進のミュージシャンに演奏されて愛されている曲です。モンクは終始ご満悦で、ずっと唸り声が聞こえます。代表曲ではありますが、所謂モンク節は少な目なのにモンクの演奏とわかるのが、また本家。「Evidence」これはモンク節の権化のような楽曲で、メロディもそうなんですが、コードをタイミングが他の曲では節目節目にモンクが入ってくるのですが、この曲はずっとモンクで、この入れ方で更にスイング感が増しているような気もする魔法の旋律です。セミの鳴き声のようなモンクの唸り声はもう一つのBGM。
「misterioso(ミステリオーソ)」とは、「カンタービレ」「マエストーソ」と同様、音楽用語「発想標語」の一つであり、神秘的に奏でよという標語です。なるほど🎶🎹
piano : Thelonious Monk
tenor sax : Johnny Griffin
bass : Ahmed Abdul Malik
drums : Roy Haynes
producer : Orrin Keepnews
painting : Giorgio De Chirico
recorded at the Five Spot Café, New York City, July 9, 1958 & August 7, 1958
1. Nutty (Thelonious Monk)
2. Blues Five Spot (Thelonious Monk)
3. Let's Cool One (Thelonious Monk)
4. In Walked Bud (Thelonious Monk)
5. Just A Gigol (Irving Caesar, Leonello Casucci)
6. Misterioso (Thelonious Monk)
7. 'Round Midnight (Thelonious Monk)
8. Evidence (Thelonious Monk)