札幌在住時代に購入したものです。Katzumaって響きなんでてっきり日本人かと思っていたら、イタリア人のボローニャの新鋭デュオとのことです。詳細はネットを見ていても実はよくわからんのですが、どうやら Andrea Visani が核となっているユニットと書いてあり、また自身が運営する自主レーベルとなっていたのでこの人の別名は Katzuma?でもあるのでしょうか。ユニットのメンツは Chico MD & Tony T と書いてあるものもあり、ボーカルはこの二人で、打ち込みで音を作成しているのが Andrea Visani なのか別人なのか?は実は未だ理解できません。写真の人の名前は?さて誰なのか???
とずっと思っていましたが、ライナーノーツをよく読んでみれば色々書いてありました。イタリアのDJユニットであることは正解。基本的にはサンプラーを使って音楽を作りはじめ、DJユニットではあるが、キーボード、ギター、ドラム、ベースもできるマルチプレイヤーであること。Katzuma は日本人の名前から由来しているが綴りは間違っていること。なので、Katzuma はユニット名で Andrea Visani は二人のうちのリーダーの名前のようです。
人物像もよくわかりませんが、サウンドは本物。アルバムを再度聴いてレビューしてみます。Bust A Loose ディスコっぽいサウンドなんですが機械的でなく、生楽器が使われているので感覚がバグるソウルナンバーです。サンプリングの究極進化系です。My Kind Of Trust これも本筋はソウルで歌の元ネタは T.O.P. でしょうか。ホーンが気持ちよく、どこかで聞いたことのある懐かしメロディーにスペーシーなサウンド。With Time これはPCで制作っぽいベースラインのループと生楽器の取り合わせですが感覚はバグらない デジタル・ソウル・ファンクです。少しチープなサウンドが魅力です。Grooving With My Good Eye Closed これもハイセンスな デジタル・ソウル・ファンク。ベースソロなのかリフなのかよくわからないベースが中心になっているのが凄いです。ループネタでよくあるようなドラムを組み合わせているチープさが、この曲も良いです。Take The Evil Spirits Away ライナーノツでは Rituals Of Life のテーマが 0:40 + Take The Evil Spirits Away 4:11 で1曲になっています。怪しげでスペーシーで凝ったアレンジのファンク・タイプのアシッド・ジャズの大曲です。作っているほうが楽しかったのかと予測します。フルート入れるとこの手の怪しさが増幅します。Keep It In The Family インコグタイプのジャズ・ファンクで大好きなタイプの楽曲です。最近思うのですが、この曲調とサウンド構成は、ほぼ当たりしかないのですが微妙な違いで曲が区別もできるけど基本は一緒ですよね。ブルースが似たような曲ばかりだけど違う曲が無数にあるのと、似てますよねえ。Boogie To This 最初は師匠 James Brown のサンプリングっぽく J.B. サウンド強めのE.W.F タイプのコーラスも入れたファンクです。ありきたりのアレンジのような気もしますが、ツボの押さえ方に非常に共感します。Let's Do It In The Hay メロー・ソウル風のデジタル音楽です。ここら辺の楽曲になってくると、サンプリングの集合体ではなく立派な楽曲です。歌いまわしとコーラスはやはり E.W.F 的です。Dogs Of War 曲名のつけ方は P-Funk だなと思ったら、やっぱりそっち系です。ゆっくりめミディアム・テンポの重めファンクで、これも私の好物。Getting Thru Your Own Thang 締めは大事です。最後はアフロ系ビートのデジタル・ファンクとなりお祭り的でループする単純なリフが少しづつ変化しながら、重低音系を足してノリをズンズンと足しながらパーカッションを重ねて更にグルーブ感を出す。
ディスコ、ソウル、ファンク、フュージョン・ジャズ、ダブ、アフロ・ビート等なんでもありで、イタリアってイメージは余り感じません。サウンドを聴いていてもPCを駆使した打ち込みとサンプリングなどで楽曲は作成されていて、アシッド的ジャズ・ファンクで非常に楽しいアルバムです。Rituals は儀式の意とのこと🎶
producer : Andrea Visani
1. Bust A Loose (Vocals : Sean Martin)
2. My Kind Of Trust (Vocals : Al Castellana)
3. With Time (Vocals : W. Time & The Oooh)
4. Grooving With My Good Eye Closed (Vocals : Gloria Tatangelo)
5. Rituals Of Life / Take The Evil Spirits Away (Vocals : Possessed)
6. Keep It In The Family (Vocals : Juglia)
7. Boogie To This (Vocals : Larry & The Boogies)
8. Let's Do It In The Hay (Vocals : Johnny Boy & The Neffertones)
9. Dogs Of War
10. Getting Thru Your Own Thang (Vocals : Own Thang)







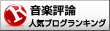











:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-2303876-1498758580-7957.jpeg.jpg)








