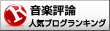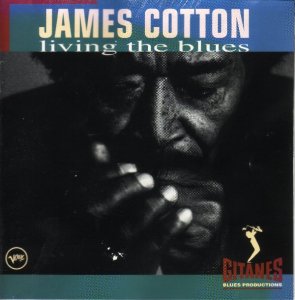1993年の作品で、中古購入ではなく発売と同時に購入した1993年のアルバム。この頃は関西在住で、David Sanbornのファンだったこともあり Murcus Miller, Hiram Bullock のソロも買い集めていた時期です。その後のソロも買い集めていますが、非常に多作な人なので、この作品を全て揃えているわけではありませんが、このアルバムを超えるものには出会っていないので、私的には、この作品が Murcus ソロの最高傑作かと思います。
私の所持する Murcus ソロは、Suddenly (1983), The Sun Don't Lie (1993), Tales (1995), Live & More (1997), Renaissance (2012), Afrodeezia (2015) となっています。
Murcus Miller は1959年のニューヨークに生まれ。父親のいとこであるジャズピアニストのWynton Kelly は父親の従妹、また父親の仕事は教会のオルガン奏者であったこともあり、小さい頃はクラリネットを手にして、ジャズやクラシック音楽に没頭。13歳の時、TVで見た The Jackson 5 をきっかけにエレクトリックベースを手にしてポップスやR&Bを始め、15歳から、プロ・ミュージシャンとして活動を開始し、1979年にはスタジオ・ミュージシャンとして活躍するようになり、Grover Washington Jr / Winelight (1982)、Donald Fagen / The Nightfly (1982)、The Brecker Brothers / Detente (1980)、渡辺香津美 / TO CHI KA (1980)、 渡辺貞夫 / Orange Express (1981) などに参加し、1981年には、Miles Davis / The Man With the Horn (1981)に抜擢されています。こうやって書き出してみると、Murcus のベースを相当聴いています。
それでは改めて全曲聴きながらレビューしていきます。「Panther」 イントロは、Chick Corea の Spain を連想するスパニッシュな印象のテーマをベース・オンリーで始め、そこらからドラムと2番目のギターソロ以外は、全てマーカスによる多重録音で作られているベースを前面に押し出したフュージョン作品です。「Steveland」は、David Sanborn、Wayne Shorter の二人をサックスに起用する豪華布陣をバックに、ベースでライトハンドとスラップでメロディー楽器として使用すしています。Jonathan Butler のアコギが渋く最後の David Sanborn のソロはいつものヤツで、安心のマーカス・サウンド。「Rampage」は、Miles Davis のマーカスをはじめとする若手を起用したファンク・アルバム Amandla の録音の未発表曲です、親分 Miles Davis が参加しています。「The Sun Don't Lie」アルバムのテーマ曲になります。フレットレス・ベースを使ったテーマがとジャコを意識したような指弾きのベース、マーカス得意のスラップと曲の流れによって奏法を変えています。Andy Narell のスチールドラムが、またジャコを指揮している感じですが、テーマのメロディーが良いです。
「Scoop」は ギラギラしたスラップとキャッチーなテーマがとてもカッコ良い曲で、Kenny Garrett のソロが、またイケてますしノリノリでフレーズで遊びまくるマーカスが素晴らしい。この曲の作り方はサンボーン系です。「Mr.Pastorius」はタイトルでわかるように、ジャコの追悼曲となっていて、ベースのみのソロ曲です。ジャコ的なフレーズよりスパニッシュとクラシックの融合みたいな曲でした。「Funny」ボーカル曲をインストにしたような曲で(いや最後にはボーカルが入ってくるので厳密にはインストではありませんね)テーマを吹く楽器はミュート・トランペットかと思っていたらソプラノ・サックスとなっているようです。「Moons」これもジャコをかなり意識したような曲となっています。 「Teen Town」 ジャコ・パストリアスの追悼で取り上げていているようで、スティール・ドラムで Andy Narell、ギターの Hiram Bullock の参加も嬉しいところ。「Juju」は、いかにも Murcus Miller らしく、David Sanborn かと思いきや アルトサックスは Everette Harp でした。ファンキーフュージョン全盛期の音がそのまま。「The King Is Gone」のキングは言うまでもなくMiles 事で、メンバーもマイルスゆかりの面々の追悼です。さらに「Round Midnight」がきますが、これは、日本版のみのボーナス・トラックですがかなりの良い出来かと思い、日本盤のみはもったいない。
こんな感じの作品を作り続けてくれれば・・ソロ作品をもっと買い集めても良いんですが
と改めて思う次第であります🎶
producer : Marcus Miller
recorded by : Brian A. Sperber*, Bruce Miller, Leslie Ann Jones, Marcus Miller, Peter Doell, Ray Bardani, Ray Blair, Ron McQuaig, Vittorio Zammarano, Yan Memmi
Recorded at Camel Island, New Jersey / Power Station, Right Track Recording, East Hill Studios and Soundtrack, New York / Capitol Recording Studios, Hollywood / Mankind, Encino / Battery Studios, London
Mixed at Soundtrack, Axis Studios and Right Track Recording, New York / Schnee Studios and Summa Recording Studios, Los Angeles
Mastered at Masterdisk, New York
1. Panther / Marcus Miller
bass guitar, keyboards, drum programming, bass carinet, rhythm guitar, guitar (1st half of solo) : Marcus Miller
lead guitar (2nd half of solo) : Dean Brown
drums : Poogie Bell
programmed by (sound) : Jason Miles
2. Steveland / Marcus Miller
bass guitar, keyboards, programmed by (percussion), bass clarinet : Marcus Miller
guitar : Jonathan Butler
drums : Lenny White
percussion : Don Alias
percussion (additional) : Paulinho Da Costa
alto sax : David Sanborn
tenor sax : Wayne Shorter
programmed y (sound) : Jason Miles
3. Rampage / Marcus
bass guitar, keyboards, rhythm guitar, drum programming : Marcus Miller
guitar : Vernon Reid
drums : William Calhoun
trumpet : Miles Davis
trumpet (additional) : Sal
programmed y (sound) : Jason Miles
4. The Sun Don't Lie / Marcus Miller
bass guitar, keyboards : Marcus Miller
piano : Joe Sample
drums : Michael White
percussion : Paulinho Da Costa
steel drums : Andy Narell
programmed by (sound) : Eric Persing
5.Scoop / Marcus Miller
bass guitar, keyboards, drum programming, programmed by (percussion), bass clarinet : Marcus Miller
rhythm guitar : Paul Jackson, Jr.
sampler (vocal) : Maurice White
alto sax : Kenny Garrett
6. Mr. Pastorius / Marcus Miller
bass guitar : Marcus Miller
7. Funny (All She Needs Is Love) / Marcus Miller, Boz Scaggs
bass guitar, keyboards, rhythm guitar, bass clarinet, vocals : Marcus Miller
lead guitar : Dean Brown
drums : Poogie Bell
percussion : Steve Thornton
soprano sax : Everette Harp
programmed y (sound, additional) : Jason Miles
pogrammed by (sound) : Eric Persing
8. Moons / Marcus Miller
bass guitar, keyboards, drum programming, programmed y (percussion), bass clarinet : Marcus Miller
9. Teen Town / Jaco Pastorius
bass guitar, bass clarinet : Marcus Miller
keyboards : Philippe Saisse
guitar : Hiram Bullock
drums (fill: snare drum, bass drum, cymbals) : Omar Hakim
drums (main beat: high hat, sidestick, bass drum) : Steve Ferrone
percussion : Paulinho Da Costa
congas : Don Alias
steel drums : Andy Narell
10. Juju / Murcus Miller
bass guitar, keyboards, programmed by (percussion), guitar : Marcus Miller
keyboards (additional) : Christian Wicht
drums : Poogie Bell
drums (fills) : Michael White
performer (funky countoff) : Jonathan "Juice" Miller, Julian "Juju" Miller
alto sax : Everette Harp
tenor sax : Kirk Whalum
programmed by (sound, additional) : Philippe Saisse
programmed by (sound) : Eric Persing
11. The King Is Gone (For Miles)
bass clarinet, bass guitar, keyboards : Marcus Miller
drums : Tony Williams
soprano sax, tenor sax : Wayne Shorter
programmed by (sound) : Eric Persing
12. Round Midnight / Berni Hanighen, Cootie Williams, Thelonius Monk
bass clarinet, bass guitar : Marcus Miller
piano : Joe Sample
drums : Tony Williams
keyboards : Philippe Saisse
tenor sax : Everette Harp
trumpet : Tom Browne
vocals : Lalah Hathaway
▶ Panther
▶ Moons
▶ Juju