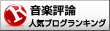Freddie Hubbard(フレディ・ハバード)は、1970~1975年までCTI時代に8枚ほどのアルバムを遺していますが、これはその移籍の第一弾の作品となります。ライナーノーツで初めて知ったのでCTIは、このアルバムのプロデューサーの Creed Taylor が1970年に独立したレーベル、Creed Taylor Incorporated の略だということ。CTIと言えばストリングスを加えたイージーリスニング路線のイメージですが、ここら辺は社長の Creed Taylor の戦略と言いうところが大きいようで、低迷するジャズ音楽業界に一石を投じるフリージャズに対しても、今後のジャズの在り方を自分のレーベルを作って体現していたようであります。個人的にはCTIのヒット作 Wes Montgomery / A Day In The Life なんかは余り好きではないのですが、なぜあのアルバムが出たのかが理解できました。
さて、このアルバムの Freddie Hubbard のバンドは2管クインテットのジャズ・フォーマットでストリングは入っていません。編成は古いタイプでありますが、ハンコックはエレピとハモンドの演奏でアコースティックは一切なしですので、あまりCTIから発売の音源と言う感じではありません。
また、音以外で気になったのはアルバムのデザイン。タイトルの Red Clay は、日本語では「赤土」ですから言葉からのイメージは、ドロドロのブルースっぽい曲が連想されてもよさそうですが、ジャケットは赤土の砂埃の中に月か太陽が見えるかのようなSFチックなデザインです。カバー写真は、Price Givens、アルバム・デザインは Tony Lane。ライナーノーツは赤土がひび割れたモノクロ写真がバックになっています。この赤土の意味合い、こだわりがどういったものかは、調べてもよくわからなかったのが、今回は残念です。
といったところで、再度聴きながらのレビューですが、先ず最初に、このアルバムは全曲 Freddie Hubbard のオリジナルです。Red Clay 最初に聴いた音楽好きの集まる「おでんバー」では、人と話していたので聴き流していたのですが、ジャズ・フォーマットと思っていたのが中身はフュージョンですね。ドラムは8ビートだし、Ron Carter のベースはジャズ・ファンクです。最初はジャズっぽいこともやっているんですが、曲が進めばコード進行もジャズファンクの流れ。Hancockのエレピも、まさにそれ。「おでんバー」仲間には好まれない流れではありますので聞き流されてしまったのは、このせいですね。今晩もう一回持って行ってかけて反応を見ようと思います。何故「赤土」なんだろう? Delphia これもジャズっぽいけどフュージョンの流れです。サンボーンとかでも、この流れありますね。ブルース形式ではありますが、ちっとも泥臭くない。でも良い意味で古臭い。曲名が何を指すのか気になりましたが、Delphia の検索で出てくるのはヨットの販売会社ばかりです。人名なのか?もしかしたら Philadelphia の略? Suite Sioux 非常にジャズっぽい曲です。っていうかフュージョンっぽくない。これも曲名の Sioux が気になりましたので調べて見ると、先住する北米インディアンの諸部族のことです。インディアンと暮らす?を感じる曲調ではありませんので、これも不明ですね。The Intrepid Fox これはロンドンのパブがヒットしました。ただこの名前で開かれていたのは1997~1999年とのことで1784年に Samuel House の名前で開店したとのことなので疑問は深まります。曲としてはハード・バップスタイルです。Ron Carter のベースもそれなのですが現代的な音がします。曲としてはハード・バップですが、Hancock のエレピが、アコースティックでは出せないノリを産み出しますし Freddie Hubbard の吹きまくりのソロ、Joe Henderson の独特の雰囲気の作り方と間が良いです。
あからさまなフュージョン路線ではない中途半端なところが魅力で、再度聴き直すと最初よりも味が出てきたアルバムになります。私のCD棚のヘビ・ロテ枠に収納しようか、どうしようか迷います🎵
trumpet : Freddie Hubbard
tenor sax, flute : Joe Henderson
electric piano, hammond organ : Herbie Hancock
bass : Ron Carter
drums : Lenny White
producer : Creed Taylor
recorded at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey, January 27–29, 1970