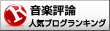アルバムごとに綿密に構築したコンセプトで度肝が抜かれますが、通算5作目となる今作は優しいメロディーラインの、Esperanza(エスペランザ)ではなく、激しい感情の現れている曲が多く収録されています。前作は、グラミー賞で2部門に輝いた2012年の Radio Music Society に続く3年ぶりアルバムです。作風は違いますが、ジャズやラテン、ソウル、ファンク、アフリカンなどの要素もあり、今作でも独自の音の世界観が反映されています。
アルバム名に入っている Emily は、自身のミドルネームで、誕生日の前の晩に見た夢の中に出てきたというキャラクター(=もうひとりの自分)を主人公として、人間の「進化(Evolution)」と「退化(Devolution)」を表現するミュージカルのようなコンセプトです。やはりこのような大胆な変革にはプロデューサーの力が大きくデヴィッド・ボウイの ★ のサウンドメイキングの Tony Visconti が共同プロデュースです。
さて、アルバムのレビューをしていきましょう。最初が一番ロックしてます。Good Lava 彼女の独特のボーカル、プログレのようなギターサウンドでグイグイです。Unconditional Love これは、いつものエスペランザに近いですがポップなテーマのメロディは、ぶっ飛んでいませんので聴きやすいかもしれません。Judas プログレっぽいベースで始まるEsperanza の得意とするメロディ・ラインのジャズっぽいニュアンスが混じった曲です。このパターンが大好きです。Earth To Heaven ここではロックっぽいニュアンスが登場します。ボーカルにはラップっぽいものも取り入れてます。やはり凡人には到達できないところに彼女はいます。One エレピの弾き語りで始まりますが、破壊的な和音の歪んだギターでガツンとかまされポップさも入れてきます。広がる世界観が壮大な曲です。Rest In Pleasure 曲名からして少し大人しい曲なのかと思いきや、中東的な音階や不思議感のある曲で妙なリズムが面白い。Ebony And Ivy お経みたいな早口の言葉で始めるアイデアにビックリですが、プログレになっていくのが更にビックリ。Noble Nobles アコースティック・ギターを活用した幻想的な Esperanza 流フォーク・ソングで Joni Mitchell の流れです。これも大好きなヤツです。Farewell Dolly アコースティック・ベースにコーラスをかけて弾き語りとなっています。短いですがこれも良い。Elevate Or Operate 近未来的な響きがします。ポップスのコード進行を入れながら複雑な展開をしていきます。Funk The Fear Oz ファンクと名をつけているので、Esperanza 流ファンク・ミュージックがこれのようです。でもファンカデリックに、これはデキマイ。精神は理解できました。I Want It Now そろそろ甘い曲があっても良いのではないかなと思ってきましたが、今回の Esperanza は S が裏テーマのような作品ですからそうはいきません。とってもホラーな曲で、ニナ・ハーゲンも感じます。ここからは日本版のボーナス・トラックです。Change Us 普通にロックを歌っているのが不思議ですが、普通の曲を歌っても良いです。ファンとしては鳥肌も立ちます。この路線をアルバムに1曲入れても良いのでは? Unconditional Love 2曲目の Altenative Version で、ソフトロック路線のような感じです。2曲目は意識的にポップなアレンジにしたのがよくわかります。Tamblien Detroit ボーナスの最後に、またダークなヤツを持ってきています。
最初にこれを聴いた時には、疲れたと過去に書いてありました。今はそんなことはありません。不思議な世界観は健在でいながら、ミュージカルのようでオペラ・ロックのような素晴らしいアルバムです。今まで聴いてこなかった人には、天才過ぎてやばい人に思えますので最初の頃の他のアルバムも一緒に購入されることをお勧めします🎶
vocal, bass (1-11, 13, 14)), piano (10, 12), bass synthesaizer (12) : Esperanza Spalding
backing vocals (1, 2, 5-7, 12-14), synthesizer (6), trombone (8), keyboards (12): Corey King (1, 2, 5-7, 12-14),
backing vocals (1, 6, 11, 12, 14) : Emily Elbert
backing vocals (2, 5, 7, 13) : Nadia Washington
backing vocals (11) : Celeste Butler, Fred Martin, Katriz Trinidad, Kimberly L. Cook-Ratliff
drums : Justin Tyson (1, 6, 11, 12, 14), Karriem Riggins (2-5, 7, 8, 10, 13)
guitar : Matthew Stevens
percussion : Karriem Riggins (9)
producer : Esperanza Spalding, Tony Visconti
recorded at NRG Studios, North Hollywood, California, Magic Shop, New York City, HUMAN, New York City
1. Good Lava
2. Unconditional Love
3. Judas
4. Earth To Heaven
5. One
6. Rest In Pleasure
7. Ebony And Ivy
8. Noble Nobles (Esperanza Spalding, Corey King)
9. Farewell Dolly
10. Elevate Or Operate
11. Funk The Fear
12. I Want It Now (Anthony Newley, Leslie Bricusse)
【Bonus Tracks】
13. Change Us
14. Unconditional Love (Altenative Version)
15. Tamblien Detroit
▶ Judas