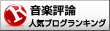1940年代末から1950年代のはじめにかけて、パーカー派のスタイルを踏襲したアルト・サックス奏者として活躍したのは、Sonny Stitt (ソニー・スティット)、James Moody (ジェイムス・ムーディ)、Lou Donaldson (ルー・ドナルドソン)の3人でした。
もともとは10インチLP2枚で発売されていたルー・ドナルドソンの初リーダー・アルバムを12インチ時代に入って一部をカットして1枚にまとめられたものらしい。本CDはその録音に更にAlternate Takeを5曲を加えたものとなっています。邦題としては「ハード・バップセッションズ」と付けられていて、LPでの発売のものとは曲順なども異なるものとなっています。録音は1952年6月20日の初リーダー・セッションとなったカルテット。続いて11月19日のトランペットのブルー・ミッチェルを含めたクインテット。そして1954年8月22日のトランペットにケニー・ドーハム、トロンボーンにマシュー・ジーを迎えてのセクステットとなっています。
タイトル通り3種類の編成によるストレートなジャズが聴けるもので、ルー・ドナルドソン自体はバップアクセントは少な目でスムーズな演奏です。ハード・バップ・セッションズという邦題ではありますが、50年代初めはハード・バップが確立、認識される前のものですあるにもかかわらずハード・バップ的なプレイが見られるのも、このメンバーの演奏であったからこそと興味深いものがあり、邦題だけ見たときに時代が違うのでは?と思ったのに対し、この演奏にこの邦題を付けたことにも納得がいきます。
シルヴァー、ブレイキー、ドーハムという強力なメンバーでの初期メッセンジャーズのメンバーが参加していることに注目して聴いていると、ブレイキーのいない演奏、シルバーのいない演奏などはこんな風になっているのかと思いながら聴いていると更に面白く聴けるのではないでしょうか。また1952年と54年の録音ではありますが、演奏の質はまったく古さを感じさせずアルバムとしての流れと統一感があるのは、さすがブルーノートを支えたプロデューサー Alfred Lion だと感心します。
1~7曲目はホレス・シルバーを中心としたピアノ・トリオで Roccus、Cheek To Cheek、Lou's Blues は Alternate Take が収録されている。8~11曲目は、アートブレイキーを含むホレス・シルバーのトリオにブルー・ミッチェルが加わってのクインテットとなり、ブレイキーが加わると演奏が楽し気になっているように私には聞こえます。12~15曲目は、トランペットがケニードーハムに変わりトロンボーンのマシュー・ジーが加わり3管編成となり、ピアノはエルモ・ホープにチェンジします。全員ノビノビとした演奏に拍車がかかり3管ならではの華やかさ、ルーのサックスも増々滑らかになっているように聴こえます。トリオならコンパクトにジャズのお手本のようにまとめた Roccus、古き良き時代のようなものを感じルーのソロも滑らかな Cheek To Cheek、クインテットでは、The Best Things In Life Are Free、セクステットでは、Caracas ブレイキーのドラムソロから始まる After You've Gone なんかが好印象です。
アート・ブレイキーの A Night At Birdland は1954年2月21日のことでした。本作の1954年録音は8月22日で、それ以外は1952年の録音です。メッセンジャーズの源流はここにも流れていたんですね🎵
alto sax : Lou Donaldson
piano : Horace Silver (1 to 11), Elmo Hope (12 to 15)
bass : Gene Ramey (1 to 7), Percy Heath (8 to 15)
drums : Arthur Taylor (1 to 7), Art Blakey (8 to 15),
Trombone : Matthew Gee (12 to 15)
Trumpet : Blue Mitchell (8 to 15), Kenny Dorham (12 to 15)
producer : Alfred Lion
1-7: recorded at WOR Studios, New York City on June 20, 1952.
8-11: recorded at WOR Studios on November 19, 1952.
12-15: recorded at the Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey on August 22, 1954.
1. Roccus (Alternate Take)
2. Roccus
3. Cheek To Cheek (Alternate Take)
4. Lou's Blues (Alternate Take)
5. Lou's Blues
6. Cheek To Cheek
7. The Things We Did Last Summer
8. Sweet Juice
9. Down Home
10. The Best Things In Life Are Free
11. If I Love Again
12. Caracas
13. The Stroller
14. Moe's Bluff
15. After You've Gone
▶ Roccus