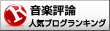本作はサックス奏者の Hank Mobley がリーダーとなって、1957 年にBlue Noteレーベルから BLP 1540 としてリリースしたアルバム。モブレーは、このセッションのリーダーであり、全てモブレー作曲となります。しかしソロなどの出番が特に多くなっている訳ではなく、自分は余り目立たずに「皆さん自由にやりなはれ」といった感じです。
改めてメンバーはHank Mobley(ts), Donald Byrd, Lee Morgan(tp), Horace Silver(p), Paul Chambers(b), Charlie Pership(ds)で、トランぺッターを2人配置している変則編成です。サックスの調子は基本テナーとソプラノはB♭、トランペットも同じくB♭です。通常は管楽器は調子の違う楽器でバンドを編成することによって、アンサンブルを構成するのですが、あえて同じB♭3管編成は珍しいような気がします。ライナー・ノーツでは「そのような音域の制限から、クローズド・ボイシングと、ユニゾンのメロディライン、3度を使った3声のボイシングを取り入れた」と書いてあります。楽器をやらない人には何のこっちゃで、楽器をやる人はフーンと思っていただけるのかと思います。
収録曲は、なんと4曲という割と1曲が長めのアルバムです。1曲目の Touch And Go は騒がしいファンファーレ風のイントロとブレイクがウルトラQみたいな怪獣が出てきそうな感じで始まります。テーマには簡潔な3音のラテン風味のフレーズが使われていて、Horace Silver の切り込み隊長からエキサイティングなソロ、続いては Lee Morgan 18歳にしては早熟な演奏は相変わらず。続いてはモブレーのソロはアダルトに控えめに始めて段々と饒舌になり、Donald Byrd の鋭きソロに引き継いで、Paul Chambers のよくあるアルコ・ソロ、Charlie Persipドラム・ソロは簡潔にまとめてます。そこからはトランぺッター二人の乱れうちです。続いて Double Whammy も明るいテーマの曲ですが少しアダルト。ソロ回しはMobley→Morgan→Byrd→Silver→テーマ→Persip、そしてまたもや Byrd⇔Morgan の合戦で、うん楽しい。Barrel Of Funk はミディアムテンポのスイング。今度のソロ回しは、Byrd→Mobley→Morgan。Silver のピアノソロは管のソロの後の良い休息になっていて好感。 Mobleymania は曲名に自己愛を感じる明るめのテーマの楽曲。Mobley のこのアルバムでの作曲はこの雰囲気での一貫性を感じます。ここでは Morgan のソロから始まり、今までの演奏で体がほぐれてきたかのように全体的に流れるように流暢なプレイが繰り広げられる熱気あふれる演奏です。
リーダーそっちのけで競り合うプレイにばかり思わず耳が行ってしまうが、ナイスな作品でした。CDのデータは Hank Mobley Sextet でした🎶
tenor sax : Hank Mobley
trumpet : Donald Byrd, Lee Morgan
piano : Horace Silver
bass : Paul Chambers
drums : Charlie Persip
written by : Hank Mobley
producer : Alfred Lion
engineer (recording) : Rudy Van Gelder
recorded on November 25, 1956. Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey
1. Touch And Go
2. Double Whammy
3. Barrel Of Funk
4. Mobleymania