Art Blakey and Jazz messengers は1954~1955年にかけてピアノのホレス・シルヴァーと結成されました。Moanin'(1958) が代名詞のバンドで、ジャズ史に名前を刻む多くのミュージシャンを輩出しましたが、そのアートブレイキーでも低迷期があり1970年代後半ぐらいから低迷期に突入し暗黒時代と呼ばれています。
そして低迷期の脱出に、若き18歳のWynton Marsalis(ウィントン・マルサリス)の加入が一役買います。マルサリスのメッセンジャーズ入団は、1980年6月のボトムラインでのライブからで、このライブ録音はその半年後の 1980年10月11日フロリダ での録音。このライブを経てのスタジオ初録音は Album of the Year (1981年4月12日パリでの録音) 。ライナーノーツによると、この録音は1981年83年85年の3回にわたって、マルサリス名義でフーズ・フーと言うレーベルから発売されていて、それを一つのアルバムにまとめての再販となったものであるとのこと。
もともとのマルサリス発売のアルバムには曲名やクレジットに誤りがあったらしいですが、このアルバムでもまずは重大な間違いを発見しました。アルバム・ジャケットをよく見ると「Messengers」が「Messangers」のになっています。再発盤であり関わった人も少ないのかもしれないですし、ジャケットの絵とかデザインもやる気は感じられず、まあご愛嬌でしょうか(CD自体にもMessangers の印字です)このレビューを書いていなければ私も気づかなかったとは思いますが、音楽業界の文字誤植は結構多いですが、私の勤める業界では誤植はご法度。かなり厳しくて製品名が間違っていたりしたら即回収、即改版ですね。
と間違いを発見したところでアルバムですが、新しさは感じます。派手なメッセンジャーズの演奏が更に大袈裟な表現になっているようです。ブレーキー親分なんて関係ないといったようなマルサリスのトランペットの加入により、バンドの音の表情がはっきりしている感じがします。親分も懐が深くメンバーのネオ・ハードバップな解釈、新しい響きとアプローチに対してドラムはその新しい響きに反応しています。前半は様子見のような感じもしますが後半では完全に見切ってバンドをリードし鼓舞しているところはさすがです。また十八番である Moanin' の新しいアプローチが施されているところも新生メッセンジャーズの意気込みが感じられますが、ベースソロの前の親分のミスっぽいブレイクには少しニヤリですね。そして Charles Fambrough の輪郭がはっきりとしたブルンとした音色とベースラインも好みです。全体的にはロックにも似たような力強さを感じてとても良いアルバムですが、好みは分かれるかと思います。ブレイキーに限って言えば、初期のブレイキー親分の「どうだこの野郎!」的な演奏の方が好みかもしれません。(聴きこむと変わってくることもよくあるし、1年後には好みが変化することもあるので今のところはですが)🎶🥁
drums : Art Blakey
alto sax : Bobby Watson
tenor sax : Billy Pierce
trumpet : Wynton Marsalis
piano : Jimmy Williams
bass : Charles Fambrough
recorded in Fort Lauderdale, Florida, Bubba's Jazz Restaurant, October 11, 1980.
【Disc1】
1. Angel Eyes
2. Bitter Dose
3. Wheel Within A Wheel
4. Gipsy
5. Moanin'
6. Au Privave
7. Free For All
【Disc2】
1. One By One
2. My Funny Valentine
3. 'Round About Midnight
4. ETA
5. Time Will Tell
6. Soulful Mister Timmons
7. Blakey's Theme
▶ ETA







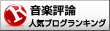















.png)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)