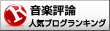一聴して感じるのは正調で凛々しいサウンドで、とても良質なこと。チューバ、ユーフォニウムなどを加えた5管オクテットからなる8人編成のモブレーの力作です。
このアルバムは1966年3月18日に Blue Note で録音されたのですが、1979年まで封印されていたアルバムとのこと。理由はよくわかりませんが、Blue Note Records は、この録音の1966年に米リバティー・レコード社に売却されていることが原因なのでしょうか?一方でライナーノーツでは、この売却によってこのレコーディングメンバーの大アンサンブルが実現したのではないか(予算が使えるようになった?)とも書かれていますが、発売されなかった理由については書かれていませんでした。
さて地味な再発盤なのかジャケットが寂しすぎるのが惜しいこのアルバム、冒頭から大絶賛してしまいましたがホント素晴らしい。そして第一に感じたのは、これだけの大編成の管がいながら、ピアノの存在感が非常に大きいことです。マッコイ・タイナー良いですね。
曲の紹介ですが、スタンダードで There's A Lull In My Life を演奏しているほかは全てモブレーのオリジナル。印象的なアクの強いテーマではないものの、すんなりとテーマを味わってメンバーがスムーズにアドリブに入っていけていて素材的に優れてるのが特徴的と思います。Hank's Other Bag は、ユーホとチューバから入りながら流れるようにテーマには入り込み、まずはマッコイ・タイナーの技に聞き入ります。Cute 'N Pretty はチューバの低音がテーマの部分で効果的に響き牧歌的な印象を与えながらも情熱的な曲となっています。 A Touch Of Blue、 A Slice Of The Top については、モーダルなアプローチで若干流すような感じもしないでは無いですが、各自のソロは天下一品。1966年のナイト・クラブで酒を飲みながらこんな曲を聴いていて騒いでいたら気持ちよく酔えたに違いない。チューバやユーフォニアムなどの多彩な楽器の中でのモブレー節が楽しいアルバムです。
tenor sax : Hank Mobley
piano : McCoy Tyner
bass : Bob Cranshaw
drums : Billy Higgins
alto sax : James Spaulding
trumpet : Lee Morgan
euphonium : Kiane Zawadi
tuba : Howard Johnson
producer : Alfred Lion
recorded on March 18, 1966 at Van Gelder Studios, Englewood Cliffs, New Jersey.
1. Hank's Other Bag
2. There's A Lull In My Life
3. Cute 'N Pretty
4. A Touch Of Blue
5. A Slice Of The Top